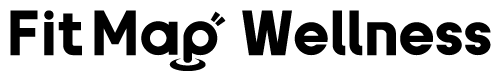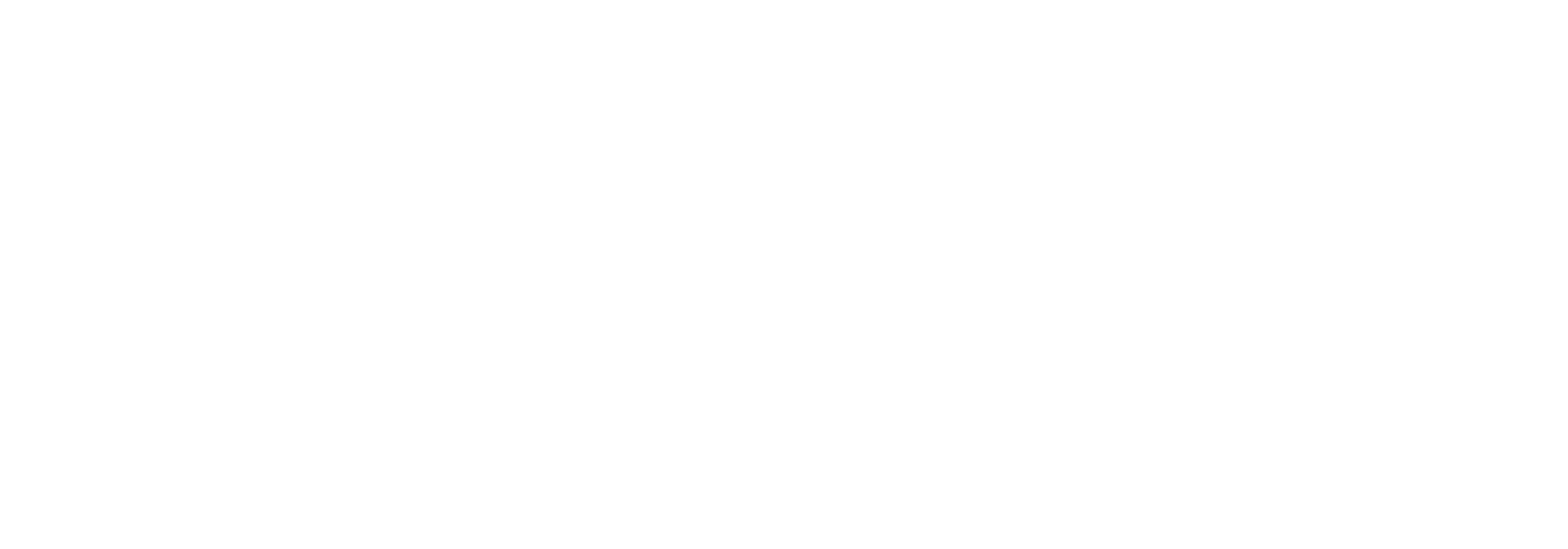「血管性認知症にならないようにしたいけど、何に注意すればいいの?」
「他の認知症と何が違うの?」
血管性認知症という言葉は知っているけど、症状や予防方法はわからないという方もいるのではないでしょうか?
血管性認知症は脳卒中による脳の機能低下が原因で起こる認知症です。
そのため、脳卒中をはじめとする生活習慣病を予防することが最大の予防といえるでしょう。
血管性認知症を予防することで生活習慣病にも繋がるので、老後もご家族や友人と楽しい時間を過ごすことができます。
本記事では血管性認知症の危険因子から症状、予防方法まで幅広く解説しているので、ぜひ最後まで読んで脳血管性認知症の予防の参考にしてみてください。

血管性認知症とは

血管性認知症とは脳梗塞や脳出血などがきっかけとなり、脳への血流が途絶えることによって生じる脳細胞の死滅が原因で発症するものをいいます。
血管性認知症はアルツハイマー型認知症に次いで2番目の多く、厚生労働省の実施した認知症に関する疫学調査によると認知症全体の約20%を占めるほどです。
血管性認知症の危険因子は生活習慣病

血管性認知症は脳卒中、主に脳出血よりも脳梗塞でなることが多く、なかでも多発性ラクナ梗塞によるものが最も多いです。
ラクナ梗塞とは穿通枝と呼ばれる細い血管が閉塞することで、穿通枝が栄養する領域の脳組織の機能低下をきたすものをいいます。
ラクナ梗塞をはじめとする脳卒中の背景には、生活習慣病を中心に以下の要因が隠れています。
- 高血圧
- 糖尿病
- 肥満
- 喫煙
これらはそれぞれが密接に関わっており、そのほとんどが日々の生活習慣が原因といえるでしょう。
高血圧
高血圧は3大疾病の脳卒中をはじめ、心筋梗塞など血流障害が原因になって生じる病気の危険因子として知られています。
過去の研究においても高血圧の合併により脳卒中の発症リスクを増大させることが報告されており、脳卒中の予防には高血圧の治療が重要であることは間違いありません。
高血圧治療ガイドラインでは診察室血圧(病院で測る血圧)140/90mmHg以上、家庭血圧(家で測る血圧)135/85mmHg以上を高血圧としており、最近では診察室血圧が130/80mmHg、家庭血圧が125/75mmHg以上でも高値血圧と診断されるほどです。
そのため、75歳未満は家庭血圧を125/75mmHg未満、75歳以上でも135/85mmHg未満に抑えるように、安定して目標となる血圧を維持することが重要になります。
(出典:一般向け「高血圧治療ガイドライン 2019」解説冊子)
糖尿病
糖尿病も脳梗塞の危険因子であり、欧米の研究では糖尿病の合併により脳梗塞の発症・死亡リスクは上昇することがわかっています。
国内のコホート研究でも糖尿病の罹患によるラクナ梗塞や塞栓性脳梗塞の発症リスクの増加が報告されており、糖尿病合併によるラクナ梗塞や塞栓性脳梗塞の発症リスクは男性でそれぞれ、2.04倍、2.85倍、女性で3.85倍、4.24倍です。
約2〜4倍の倍率を見るだけでも糖尿病の合併と脳卒中との関係性の深さが伺えるでしょう。
また、糖尿病のように血糖値が高い状態では、体内で中性脂肪が産生されやすくなったり、インスリンの活動低下による血中の脂質増加を招いたりするため、肥満や脂質異常症にもなりやすくなります。
(出典:国立研究開発法人 国立がん研究センター −糖尿病と脳卒中の病型との関連について−)
肥満
肥満の状態は脳卒中をはじめ、高血圧や脂質異常症、糖尿病、心筋梗塞などの生活習慣病のもとになるため、厚生労働省も肥満の予防を呼びかけています。
肥満は「体重(kg)」÷「身長×身長(m)」によって求められるBMI(Body Mass Index)を用いて判定されます。
BMIが18.5〜25.0が基準範囲内とされ、BMIが25.0以上で肥満と定義されます。
また、標準とされるBMI22.0は最も糖尿病や高血圧などの生活習慣病になりにくいとされています。
肥満にならないように意識することで生活習慣病を予防できれば、結果的に脳血管性認知症の発症リスクを下げることにもなるでしょう。
喫煙
喫煙による脳卒中への影響は我が国の研究データでも多く報告されています。
2000年には喫煙がラクナ梗塞の危険因子であることが発表され、男性では1.56倍、女性では1.57倍の倍率で非喫煙者よりも喫煙者が脳卒中になりやすいことが発表されました。
また海外の報告をみてみると、1日あたり20本吸っていたタバコを1本に減らしても、発症率は30〜40%までしか減少せず、予防をするなら完全に禁煙する必要があるともいわれています。
血管性認知症の特徴と経過

認知症では記憶障害、見当識障害、遂行機能障害のような中核症状に加えて、抑うつや無気力、妄想のような周辺症状(BPSD)が出現するのが一般的です。
- 記憶障害:同じことを何回も言ったり、少し前の記憶がなくなる
- 見当識障害:日にちや時間、場所がわからなくなる
- 遂行機能障害:理解力や判断力の低下、動作の方法や手順などがわからなくなる
- ものとられ妄想、自発性の低下、怒りっぽくなる、急に泣き出す
血管性認知症とアルツハイマー型認知症では、以上の認知症症状の認知症症状の出現の経過が異なります。
それぞれの違いを以下に示します。
| 血管性認知症 | アルツハイマー型認知症 | |
| 特徴 | ・脳卒中がきっかけで発症し、再発のたび段階的に進行
・症状に日内、日間変動がある(まだら認知症) ・抑うつや感情失禁がみられやすい |
・脳の萎縮とともに緩徐に発症し、緩やかに進行
・記憶、見当識障害が強く、ものとられ妄想が特徴的 ・持続して認知機能の低下がみられる |
まだら認知症
血管性認知症の1番の特徴ともいえるのが「まだら認知症」です。
まだら認知症とは脳の循環不良が原因となり、言葉どおり症状が強い状態とあまり症状がでない状態が日内や日間で差が出るような状態をいいます。
また先述したように、血管性認知症の発症は脳梗塞や脳出血による脳機能の破綻が原因です。
そのため、脳組織内で健常な部分と機能低下を起こした部分ができ、限局的に症状が出現します。
抑うつ
血管性認知症ではアルツハイマー型認知症に比べて、人格が最後まで保たれることが多い傾向にあります。
そのため、まだら認知症の状態を本人が自覚することで、自分の認知症の進行に悩むケースも多くみられます。
今までできていたことができなくなると、「こんなこともできないなんて情けない」と自分を悲観し、うつ状態になることも。
本来の認知症の周辺症状が合わさると、さらに無気力やうつ状態が強くなるので、周囲の関わり方が重要になります。
感情失禁
認知症の周辺症状として本来みられる感情失禁も、血管性認知ではアルツハイマー型認知症に比べて強くみられます。
誰しもムッとしたり悲しいことがあったりしても、大抵は自分のなかで抑えることができ、大衆の前で怒ったり泣いたりすることはないでしょう。
しかし血管性認知症では、前頭葉という人格や感情のコントロールを司る部位が脳卒中により損傷を受けることで感情が不安定になり、些細な刺激でも泣いたり怒ったりするようになります。
身体への症状の併発
脳への虚血状態による脳の組織へダメージの結果、それぞれ該当する部位の機能障害が起こるのも血管性認知症の特徴です。
手足を動かしたり感覚情報を受け取る組織がダメージを受けた際には、手足の動かしづらさや痺れが出ますし、記憶に関わる組織に影響が出ると物忘れが急激に悪くなることもあります。
また症状的に認知症と混同されやすいですが、高次脳機能障害が併発することも少なくありません。
高次脳機能障害では、道具の使用方法や手順がわからなくなる遂行機能障害や視界や音、慣れ親しんだ人の顔などあらゆるものが認識できなくなる失認など、認知症でも起こりうる症状が見られます。
症状の進行は段階的
アルツハイマー型認知症が脳の萎縮に伴いゆっくりと発症するのに対して、血管性認知症では脳卒中がきっかけで症状が出現します。
また血管性認知症の進行は脳卒中の再発のたびに段階的に進行し、梗塞部位の増加や損傷部位に応じて、手足が動かしづらさ、喋りづらさや飲み込みづらさ、パーキンソニズムのような局所的な神経症状が出現します。
血管性認知症の予防方法

血管性認知症は冒頭でも述べたように、生活習慣病との関わりが非常に強いです。
そのため、生活習慣病の予防が血管性認知症の予防にもなるので、下記に紹介するような運動や食生活の是正や内服によるコントロールが重要になります。
運動
血管性認知症の予防には運動習慣をつけることが大切です。
少なくとも毎日合計で30分を目安に運動するように心がけましょう。
可能であれば最終的に5,000〜8,000歩程度のウォーキングを目標にすることで、さらに脳卒中をはじめとする脂質異常症や糖尿病、心筋梗塞などの生活習慣病の予防や改善に繋がります。
運動はストレス解消や認知機能の改善にも有効なので、積極的に取り組むことでさらに効果が期待できるでしょう。
食生活の見直し
食の欧米化が進み、塩分や脂質の摂取が著しく増加しているなか、生活習慣病の予防には食生活の見直しは欠かせません。
血中コレステロールの増加や塩分の過剰摂取は血管内にプラークを形成し、動脈硬化を進行させることでわずかな血栓でも詰まりやすくなったり、血圧が高くなったりするので脳出血のリスクを増加させます。
厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」において高血圧予防のための塩分摂取の目安は、成人1人1日当たり男女とも6.0g/日未満に設定することが望ましいとしており、血管性認知症の予防において減塩は必須といってもいいでしょう。
また野菜は血糖値の上昇を緩やかにするほか、ビタミンによる動脈硬化予防が期待できるので、バランスよく食事に取り入れるのがおすすめです。
薬剤による治療
上記の対応に加えて投薬によるコントロールも重要な役割を担います。
脳卒中になった人の場合、降圧剤による血圧のコントロールや血液をサラサラにする抗凝固薬を使用して再び脳梗塞にならないようにするのがほとんどです。
また糖尿病や高脂血症に関しても、投薬による調整で再発リスクを減少させ、血管性認知症の予防に繋がるので、医師の指示に従い治療するようにしましょう。
生活習慣病と脂質摂取量の関係性
脂質の過剰摂取、とくに肉や乳製品などに含まれる飽和脂肪酸の多量摂取は、高LDLコレステロール血症のリスク因子となるため一般的に上限を設定するべきです。
一方、過去の研究内容をもとに行った質の高い統計解析では、脳梗塞や糖尿病、心筋梗塞の発症率と飽和脂肪酸の摂取量との間に強い関係はなかったとする報告もあり、脂質の摂取に関しては物議を醸すところでしょう。
しかし、飽和脂肪酸の制限により血中総コレステロール濃度や LDL コレステロール 濃度を下げることが健常人、脂質異常症患者でも証明されており、厚生労働省は飽和脂肪酸の上限を超えないように必要量(エネルギーの20〜30%)を摂取することを勧めています。
また脂肪酸のなかには体内で生成できないEPAやDHAなどのn-3系脂肪酸などもあり、心筋梗塞の予防や認知機能改善の効果が期待されるため、n-3系脂肪酸は青魚に多く含まれる青魚を積極的に選択して、摂取する脂質の質にも気をつけるとよいでしょう。
まとめ

血管性認知症は脳卒中により発症し、危険因子は高血圧や糖尿病、高脂血症などの「生活習慣病」です。
これらは喫煙や肥満などにより容易に発症し、増悪させる因子となります。
発症および進行の予防には、適切な運動習慣とバランスの良い食生活を意識しつつ、医師による適切な投薬処方を受けることが重要です。
本記事を参加に血管性認知症の危険因子を正しく理解して、予防に努めましょう。